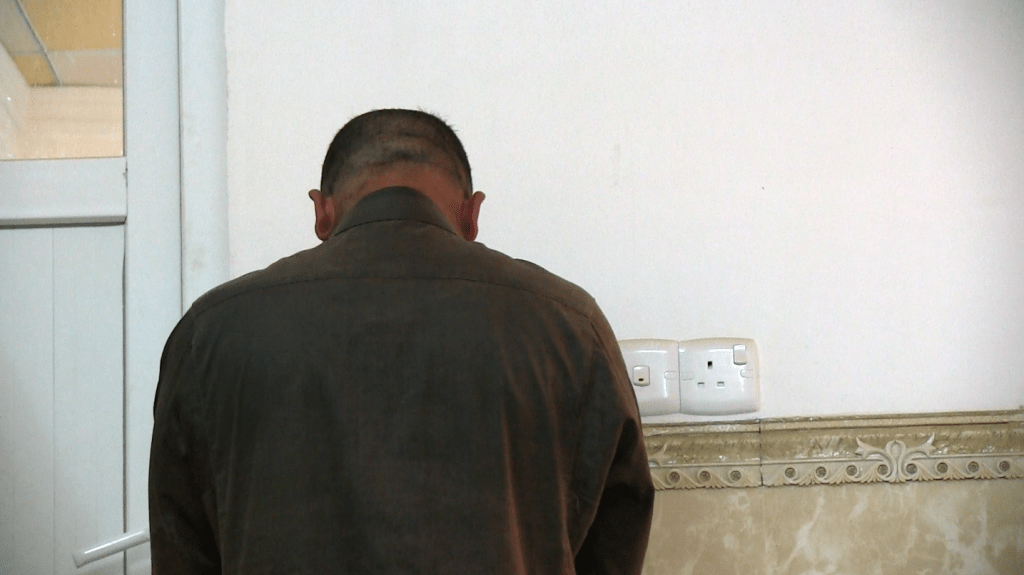友だちのお父さんはイスラム国の戦闘員
イスラム国に入る人はモンスターじゃない。だからこそ自分に近くて恐ろしい。
Videos by VICE
「同級生のお父さんが、イスラム国の戦闘員だったんだよね」
12歳の少年が大きな目でこちらをきっと見据えて答えた。彼の口から出た、「同級生のお父さん」というありふれた言葉の後に、「イスラム国の戦闘員」なんていう恐ろしい言葉が続くとは予想もしなかった。そのあまりにもミスマッチな組み合わせに再度聞き返してしまう。
私は、イスラム国に加わる人たちは、〈モンスター〉のようなもので、別世界から来るもの、とどこかで想像していたのかもしれない。イスラム国の戦闘員について、報道でなんとなく知っているつもりだった。過激思想に感化された人たち、同組織に外国から参加する不満を抱えた若者たち、貧困層の人たち、と。でも少年の話を聞くとイスラム国という組織が、顔の見えるすごく近い存在として迫ってくるのだ。
イスラム国のもとでの生活に疲れきっていたのか、少年には、その世代の子ども特有のあどけなさはない。でも臆することなく堂々と話し始めた。
§
7月上旬にイスラム国からの〈解放〉が宣言されたイラク第二の都市、モスル。軍事作戦が続行中の4月下旬、私はそこから100キロほど離れたデバガ避難民キャンプを訪ねた。イラク軍、有志連合軍が本格的なイスラム国掃討作戦を開始したのは昨年10月。周辺地域に多くの避難民が溢れ出していていた。
避難民キャンプでは仮設小学校を訪ねた。突然現れた私を、校長先生は親切に迎えてくれ、イスラム国に支配されていた当時の様子を聞かせてくれた。校長先生いわく、イスラム国戦闘員がやってくると、学校の運営はのっとられたが、教員はそのまま働き続けるよう強制された。手榴弾や武器などを携えたイスラム国の戦闘員が校内を出入りし、生徒たちに武器の使い方を教えた。国語の例文、足し算引き算の例えは、爆弾や戦車に変えられた。校長先生は、イスラム国のメンバーに知られれば処刑されるのを覚悟で、子どもたちに、学校にはもうくるな、と伝えていたそうだ。その甲斐もあって、当時、学校にくる子どもたちはほとんどいなかったという。しかし、新しい学校に通う子どもたちはエネルギーに満ちていた。イスラム国支配のもと失った2年半の学校生活の鬱憤を晴らそうとしていたのかもしれない。
心に傷を負った子どもたちもいますか、と尋ねると校長先生は、落ち着きがなかったり、問題を起こしやすい子もいる、と教えてくれた。子どもたちと直接話してみてはどうですか、と提案され、数人を紹介してもらうことになった。
12歳のアハメド(仮名)と13歳のオマール(仮名)。二人は突然、校長室に呼び出されて、まるで悪いことをしたみたいにバツの悪い顔をしている。でも変な外国人に名前は、何歳などと聞かれるので今度はニヤニヤ笑い始めたが、「イスラム国のもとでの生活を教えてほしい」と切り出すと、2人の顔つきがはっきりと変わった。
「全部壊されて、憎み合って、みんながいる前で首切りの処刑もあった。最悪だよ」。薄茶色の短い髪をカールさせたオマール少年はふてくされたように答えた。ある金曜日にモスクに行こうとすると、モスクの前で公開斬首に出くわしたそうだ。「僕はみたくなかったけれど」とオマールはぎこちなく短い言葉で答えた。
年下のアハメドのほうが話したい気持ちが強いようで、オマールとのやりとりに横槍を入れてくる。ぽちゃっとした顔のアハメドは幼くみえる。しかしその話の内容は、12歳の少年のものとは思えない。アハメドは、半ズボンなど肌の見える格好をしていると罰せられたり殺されたりすること、いとこを含め親戚4名がイスラム国の情報を政府側に流したのを理由に路上で頭を撃たれて殺されたこと、イスラム国側がいとこの遺体の写真を家族に送りつけてきたことなど、溢れるように話した。
そんなアハメドも、最初の1ヶ月だけイスラム国の運営する学校に通っていたそうだ。教科書はすべて変えられ、算数の計算は、〈1+1=2〉の例えが、「爆弾1個と爆弾1個を足すと爆弾2個」になった。斬首の方法、人の殺し方を、絵や写真を使って教えるようにまでなり、それで学校に通うのをやめたという。
学校に通い続ける子どもたちはいたのだろうか。校長先生によると、誰も登校しなくなったそうだが、アハメドは、「1人知っているよ」と教えてくれた。「村の出身の友だち。お父さんがイスラム国の戦闘員だったから」。聞き間違いだろうか。まるでパン屋やタクシー運転手だったかのように話すのだ。知り合いがイスラム国戦闘員だなんて。通訳が確認すると、アハメドは「そうだよ、同じ学校の子のお父さんがイスラム国の戦争員だったんだよ」と繰り返す。
友だちのお父さんがイスラム国戦闘員で、しかも、友だちまでイスラム国に参加した。10歳前後でイスラム国に参加するとはどういうことなのか。そこで何をしていたのか。その子はそれでよかったのか。強制されたのだろうか。堪らず尋ねると、「お父さんにすごく説得されて、お前が死んだら天国にいける、といわれてた」。アハメドは、今その子がどうしているのか、彼に何が起きたのかは知らないという。

キャンプで暮らす、とある家族を訪ねたときにも、同じ衝撃に襲われた。モスル郊外の村から逃げてきた4児の母、ムンタハさん(仮名)。その品のよい振る舞いや落ち着いた様子から、今はビニール1枚のテントで暮らしているけれど、こうなる前は、それなりの暮らしをしていたことが窺える。12〜3歳の長女は、青いヒジャーブをおしゃれにまとっていた。イスラム国に支配されるようになってから、仕方なくそうするようになったそうだ。
ムンタハさんは少し目を潤ませながら、これまでの日々を語ってくれた。「5時間歩いたり、ボートに乗ったりして逃げてきたんです。夫は、イスラム国が来てから仕事がなくて、子どもたちも学校に通えなくて…」と通訳と私の目を代わるがわる見つめた。会話が途切れると、ムンタハさんは野次馬に来ていた近所の子どもたちにその場を去るよう命じた。騒がしかったのかな、と思っていると、お母さんはこう切り出した。「夫の兄がイスラム国の戦闘員なんです」。またもや私は聞き返さなければならなかった。
彼女の夫と、彼の兄の父親には2人の妻がいて、彼らはそれぞれ別の女性から生まれた異母兄弟だ。兄は、もともとが人望厚く、地元住民にとても慕われているような人だったけれど、彼がイスラム国に参加すると、あっという間にまわりから人がいなくなった。ムンタハさんによると、イスラム国の思想に極端に傾倒した結果、同組織のメンバーになったそうだ。イスラム国からお金をもらっていた、というわけでもなく、その思想に惹かれたのが理由だろう、と彼女は説明してくれた。兄は大学の教授だった。「教育を受けてないわけじゃないんです」とムンタハさん。
そんな兄が、ムンタハさんの夫にイスラム国に加わるよう、しつこく勧誘していた。夫が断ると兄は怒り、また、兄が他の若い兄弟をも勧誘しようとしたので夫がそれを止めようとすると、さらに激しく責めた。それを目の当たりにした家族は、身の危険を感じ、住んでいた村を去らざるを得なかった。夫は鋳造の仕事をしていた。「夫は兄のような高等教育を受けていません。でも、その兄に何度も誘われて、夫自身とても悩んでいました」
キャンプに避難してからも夫は、兄と同じ名字だ、という理由で、せっかく手に入れた仕事を2度ほど解雇された。兄の行方はわからず、死んだ、という噂もある。
彼女になんと声をかければいいのかわからなかった。「ここでの生活はどうですか」。そう尋ねると、ムンタハさんはひと呼吸置いて「いいです」と答えたものの、その目からは涙がこぼれ落ちた。
モンスターの集団かのように想像していたイスラム国だが、ここで暮らす人たちの会話を聞いていると身近な存在になってくる。恐ろしさは変わらないのに、とても生活の近くいるのだ。みんなから好かれた夫の兄が参加しているのも、みんなの生活を壊したのも同じ〈イスラム国〉。いとこを殺したのも、友達の父親が参加しているのも同じ〈イスラム国〉。

イスラム国に加わるのは〈誰〉なんだろう。イラク戦争の頃から活動していた筋金入りの原理主義者、という話も聞く。あるいは、鬱憤のたまったヨーロッパ出身の若者、移民の二~三世、という話も聞く。指導部はそうなのかもしれない。実際、イラク人に「イスラム国のメンバーって誰?」と尋ねると、「もういろんな国から! アメリカ人も中国人もチェチェン人もフランス人もサウジアラビア人も!」と。でも「イラク人はいないの?」と水を向けると、「いるよ。ほとんどはイラク人」という答えが返ってくる。
2014年、180万の人口を擁するモスルは、一説によると少なくとも200人、多くてもたった1,300人のイスラム国戦闘員によって4日間で占領された(イラク軍は6万人)。その後、6,000人のイスラム国戦闘員によって支配された、と報じられている。しかし、キャンプで聞いたとおり、この巨大な街を支配するには、地元住民の関わりも少なからずあったのだろう。
モスルの公務員だった、ある男性の話が忘れられない。彼は、公務員だったのを理由に拷問された。「でもね、イスラム国が来た当初は、彼らが街を解放しにきた、と思っていたんだよ」。モスルはスンニ派が多数を占める都市だ。シーア派政権からは、長年、目の敵にされ、街の自由を奪われていた。イスラム国に拷問されたその彼が当時を思い出していうのだから、嘘、偽りはないだろう。イスラム国は、食糧を配給するなど、人心掌握に長けていたといわれる。しかし、それだけでなく、住民の心を惹きつける何かがあったのだろう。
同じ街の住民が同じ体験を共有しながら、被害者と加害者になってしまった。隣にいた学友のお父さんは、隣にいた人望ある夫の兄は、もともとモンスターだったのだろうか。イスラム国とは、いったい〈誰〉なのだろうか。
怯えた少動物のような人たち
モスルから東に30キロの街、カラコシュは、昨年10月にイスラム国から奪還された。キリスト教徒が多く暮らしていた街で、イスラム国の侵攻後、ボロボロになるまで破壊され、〈異教徒〉であるキリスト教徒たちは街を追われた。奪還後の街の入口には再建されたばかりの大きな十字架が立っていた。しかし、イスラム国への恐怖のせいで、5か月経った2017年4月の時点では戻ってきた住民はほとんどいなかった。そのカラコシュに、戦闘が続くモスルに替わり、臨時裁判所が開設されたのだ。
建物は裁判所というには大げさで、一見、ちょっと豪華な民家のようでもある。午前8時過ぎ、建物の周りの空き地に、書類を持参して順番を待つ人たちがたむろしている。イスラム国、あるいは米軍率いる有志連合軍の空爆で自宅を破壊された人々、家族を失った人々、それぞれが補償を求めて申請にきているのだ。イラク政府は、この戦争による損害を補償をする、と発表している。
しかし、同裁判所は、補償を申請するためだけにある施設ではない。聞くところによると、イスラム国戦闘員あるいは関係者である、と容疑をかけられた人たちが尋問を受けるために同施設に連行されているという。別棟でのお偉方への挨拶回りを経て、ようやく、容疑者を尋問している部屋に入ることを許された。
通された部屋ではすでに何事かが進んでいるようだった。茶色のダボダボの囚人服を着た男性が部屋の真ん中に立っている。そう、その彼がイスラム国戦闘員の容疑者だった。すでに尋問が始まっていたのだ。
「出身はどこだ」「他の仲間の名前を知っているか」。裁判官が大きな声で質問している。ありふれた造りの部屋の中でイスラム国戦闘員容疑者がすぐ目の前に立っている。手錠をはめているわけでも、横でしっかりと看守が抑えているわけでもない。裁判官らしき男性が事務机につき、緑のポロシャツを着た書記らしきスタッフが、その横で記録をとっている。部屋のまわりにはソファが置かれており、軍人やら、ピンクの派手なシャツの人やらが座っていて、ひっきりなしに人が出入りしている。あまりにもありふれた部屋。でも、間違いなくその部屋の真ん中で立っている彼が、戦闘員としてイスラム国に参加した容疑で拘束されている人物で、今、尋問されているのだ。
その男性は小柄なずんぐりした体型で、歳は50代くらいだった。頭はごつごつして、黒く日に焼けている。尋問の内容によると、19人を殺して、6人をレイプしたという。彼は、処刑された遺体を運ぶ役割も担っていた。イスラム国は独自の裁判所を設立し、軍人や市民を裁き、処刑していた。同組織は、処刑された市民たちの遺体をモスルの南にある自然にできた巨大な穴(ハスファ)に投げ入れていたそうだが、この男性は、遺体を運んだりもしたそうだ。捕まった当時、モスルの西側で自爆ベルトを装着して戦っていたという。
19人も殺し、イスラム国の内部にいた男性だ。話で聞くと恐ろしい。でも、目の前にいるのは、ただのみじめな男性にしか見えない。イスラム国に参加する以前、仕事は何だったのか、男性の弁護士だという人物が教えてくれた。「何でもする肉体労働者ですよ。家具を運んだり、ブロックを集めたり、なんでも」
大きな声で質問する裁判官と、ほとんど声の聞き取れない男とのやりとりが続く。でも、どうして彼の罪が明らかになったのだろう。弁護士が横で説明してくれた。「男が自ら、私はイスラム国の戦闘員で、罪も認める、といったんですよ。彼は、非人間的なことをしている、と自ら気づき、後悔し、それで罪を認めたんです」。イスラム国のために働き、19人も殺してしまった後で、自分のしたことが罪だったと気づく。なんとも言い難い気持ちになってしまった。殺された人間や、その家族にしてみればたまったものではない。でも、自らの罪に気づいたときの苦しみはどんなものだろう。イスラム国に参加する前に気づかなかったのだろうか。参加したとしても、19人も殺す前にもっと早く考えなかったのだろうか。そう聞きたくなった。裁判官が続ける。「イスラム国のメンバーになれば天国でよい地位に就ける、と誘われたそうです。サウジアラビアから来たアブ・ハジズという男にいろいろ聞かされた、とね」
押し黙ったままの男性。泥土を何度も踏みしめて爪の中まで泥が入り込んだのであろう汚れた足、ずんぐりとした体型。なで肩で、ごつごつした頭。きっとイラク人の大好きなチャイに砂糖を何杯も入れて飲むのだろう。もし、イスラム国がくる前に出会えたなら、ちょっとムスっとしながらも道を教えてくれたようなおじさんだったのかもしれない。彼は自分が絞首刑になるのを知っているという。

尋問が終わったところで、裁判官がこの裁判所の概要について教えてくれた。イスラム国戦闘員や関係者の容疑者たちは前線、あるいは避難民に紛れているところをイラクの警察部隊か、対テロ部隊によって捕らえられる。その後、諜報部員の検査を受け、それからイラク軍に引き渡されてこの裁判所に連行される。4~5ヶ月の間に判決が下される。裁判所はイラク各地にあるが、モスルで拘束された容疑者はすべて、ここカラコシュに連行される。容疑者は基本的にはその地域の拘置所にいて、最終的な判決はバグダッドで下される。現在、1,500~2,000の容疑者が審議を受けている。通常の裁判と同様、容疑者1人に弁護士1人がつく。弁護士のなかには国選弁護人もいる。
容疑者には、特別な法律が適用される。2005年に成立した〈対テロ法〉だ。サダム・フセイン後の混乱するイラクを治めるために施行された法律だが、イスラム国構成員にも適応されている。罪状が確定すれば、基本的には終身刑か死刑。この反テロ法は悪名高く、施行されて以来、数多の死刑を執行し、無実の市民をテロ協力者として長期間拘束してきた。シーア派政権がスンニ派市民を弾圧するために利用したといえなくもない。国際社会からの批判もあり、2016年、同法は改正され、重罪を犯していなければ釈放も認められるようになった。また、イスラム国に参加したのが2か月未満の場合など、罪に問われない可能性もある。ただし、容疑者が裁判所に連行されるまでに時間がかかるので(原則、拘束されてから24時間以内)、そのあいだに仲間から入れ知恵され、「2ヶ月しかかかわっていない」などと嘘をつくようなケースも多いそうだ。現在は、この法律改正が原因で、イスラム国の関係者が処罰されず野放しになっているのでは、との懸念もある。そのいっぽうで、カラコシュの裁判所に連行されるうちの50%が無罪だ、という声もある。しかし、ここで判決が下されるわけではないので、どれだけの容疑者が解放されて、どれだけの容疑者が有罪なのか、カラコシュの裁判所関係者にはわからないのだ。

新たに部屋に入ってきた2人目の容疑者は、弱々しい老人にしか見えなかった。彼は、イスラム国のための水の運搬に携わった疑いがあるという。囚人服がたりなかったのか、男性の上着は紺色のセーターだ。男性は最初から容疑を否認しており、彼は、イスラム国を手伝ったのではなく、もともとはドライバーをしていたけれどもイスラム国が来てから仕事がなくなったので水の運搬を始めたという。イスラム国のために働いたのではなくて、水を注文した顧客に配っただけ、そのなかにイスラム国がいただけだ、と繰り返していた。
さっきまで強い口調で話していた裁判官は、私たちに向かって、イスラム国戦闘員や協力者ではないとわかれば彼は釈放される、といった。紺色のセーターの老人はすぐに外に出ていった。
次に現れたのは、頭髪を綺麗に剃った男性だ。年齢は32歳、小学校には通ったけれど、その後の教育は受けていないという。彼は、月100ドルもらえる、と聞いてイスラム国に参加した。同時期に、イスラム国に15人の仲間がいた。そこで、宗教コースか戦闘トレーニング・コースを受けなければならなかったので、彼は戦闘トレーニング・コースに参加したそうだ。自分が参加していたのは2ヶ月だけで、父親に説得されてイスラム国を去ったという。男性はイスラム国が好きだったわけではなく、お金がほしかっただけだ、と説明した。本当は学校の先生になりたかったらしく、ヨーロッパに行きたいそうだ。
「なんでイスラム国に入ったの?」。やりとりの始まりは自然だった。一緒に取材していた地元のジャーナリストが、壁を向いて立たされていた男性にそう尋ねた。男性は「イスラム国が好きだったわけではない。お金がほしかっただけ。あと、結婚できると聞いたから」と答えた。後ろを向いたまま繰り返し答えている。言い訳がましく説明するところが妙におかしかった。彼が後悔しているのかどうかは想像するしかない。でも生き延びるためだったらイスラム国を信じている「ふり」も、後悔している「ふり」もする。したたかなのだ。男性に「良心」があるかもしれないと考えるより先に、親近感を覚えてしまった。裁判官が、男性の答えを解説しようとするが、ジャーナリストはかまわず話しかける。「えーっと、それまで何をしていたの?」。アラビア語なので詳細はわからないが、ごく普通に、ジャーナリストは「あのさ」「ねえねえ」と男性に話しかける。すると男性は、裁判官に壁に向かえ、と命じられたのに、ジャーナリストのほうに振り返ろうとする。最初は、質問がよく聞こえないのか、もしくは、意図を汲み取れないのか、裁判官のほうを見るついでに、ちらり、と振り返っていた。しかし、ジャーナリストが質問続けると、男はジャーナリストの顔をしっかりと見て返事をしようとするのだ。話しかけられたらつい相手の顔をみてしまう。後ろを向けと命じられていたのに、聞かれるから、わかってほしいから、相手の目を見て答えてしまう。それもまたあまりに人間的だった。
「子どもに首を切るところ見せられる?」「それは難しいかな」。「自分のことを人間だと思う?」とジャーナリストが質問をすると、男性は「私は人間。イスラム国にいるときは人間だとは思わなかった。でも今は人間だと思う」と答えた。

選択肢ない人たち
イスラム国戦闘員だという容疑者たちの背中を見ながら想像した。戦闘員になる以前、彼らが誰かのお父さんやおじさんだった頃を。汗を流して働いていた1日があったことを。そんな感傷に浸っていると、最後に裁判官は私たちにこう言った。「あんたたちは運がいい。今日の容疑者はそれほど残酷じゃない。他の日には100人殺したという戦闘員もいた」
部屋を出ると、今も誰かのお父さんやおじさんであり続ける人たちが佇んでいた。イスラム国に家を破壊され、家族を失った人たち。これからの生活を憂い、補償を得ようと書類をしっかりとつかんで裁判所に出入りしている。
昨年末の空爆で兄弟を失ったという男性が話をしてくれた。彼によると、イスラム国を標的にした有志連合軍による空爆の直接の巻き添えは免れたものの、同組織が意図的に停めた、武器を積載した自動車が空爆によって爆発し、兄弟がその巻き添えになって死亡したという。イスラム国は民間の犠牲者を増やし、有志連合軍に間接的ダメージを与えようとしているそうだ。話を聞いた男性の後ろには、亡くなった彼の兄弟の妻、7、8歳の息子、年老いた父親が不安そうに座ってこちらを見ている。最初は顔を隠してカメラを避けようとしていた妻も、途中からたまらず、子どもたちは傷を負っている、と話し始めた。男の子の頭には破片が食い込んでおり、彼女の頭、腕、胸にも破片が残っている、と訴えた。
彼らはイスラム国だけでなく、空爆する有志連合軍も恨むのだろうか。しかし兄弟の男性はいう。「空爆が始まって嬉しかった。解放されると思ったから。イスラム国が支配するようになってから物資が来なくなって本当に空腹だったから」。兄弟を失ったのに、その原因の1つである空爆を望む。空爆かイスラム国支配か、イラクには最悪の選択肢しかもう残っていないのだろうか。
3月17日、モスル西岸地区のイスラム国を標的にした大規模な米軍の空爆があった。米軍が認めただけでも100人以上、実際はさらに多く約300人が死亡したという、ニュースでも大きく報じられた出来事だ。多くの犠牲者を数えた原因は、トランプ政権発足以降、交戦規定が緩み、民間人の受ける被害に十分な配慮がなされない傾向が強まったからだ。また、イスラム国が地域住民を〈人間の盾〉として利用しているからだ、ともいわれている。モスル西岸地区を逃れたグループの1人の男性は、「西モスルでの勝利はない。みなが家を壊され、家族の誰かを失っているのだから。これは軍と軍との戦いじゃない、軍とネズミの戦いだ」という。別のグループには、夫をイスラム国に処刑された人、家族がイラク軍人であることをイスラム国に責められ母を殺された人、家を空爆で壊され逃げる途中にミサイルで負傷した人、放置されたままの空爆の犠牲者を来る日も来る日も庭に埋めているという人、何者かに娘の夫を誘拐されたという人がいた。
イスラム国の攻撃と有志連合軍の空爆、双方の被害者がいる。何が原因で怪我をしたのか、殺されたのかわからない被害者もいる。誰を恨み、責めればいいのだろう。それすらできない人がいる。そんな人たちが、日に200から300件もの被害申請を裁判所に持ち込む。日に日に補償を求める人は増えるばかり。しかし、イラク政府の財政状況は、決して良いわけではない。いつ補償をもらえるのか、どれほどもらえるのか、誰も知らないのだ。

〈モンスター〉を裁いているのか
カラコシュの裁判所には、3万人を擁する巨大な避難民キャンプ〈ハマム・アリル〉で容疑をかけられ、連行された、イスラム国戦闘員容疑者もいた。そのキャンプは、さながら世紀末かのような光景だった。キャンプに面した通りには、ぐしゃんと潰れた建物が転がっていた。前線の住民を載せた、青と水色の波模様があしらわれた白い大型バスが次々と到着しては出発する。バスが鳴らすクラクションの高い音、エンジンの低い音、疲労と興奮と安堵の入り混じった様子の人たちが放つ迫力。むき出しの砂の大地から巻き上がる風が人々の心をからかうように吹き抜けた。
到着した避難民の男性だけ、フェンスで囲まれたいっ画に連れていかれる。彼らはそこで〈スクリーニング〉を受ける。スクリーニングとは、避難民に紛れ込んだイスラム国構成員を探し出す手続きだ。男性たちがイラク軍兵士の指図に従い並んでいる。みな顎髭をたくわえていて、よれよれのポロシャツやパーカー姿だ。彼らは神妙な顔つきで、何が起きるのかを待っていた。
私と通訳が様子を窺っていると、グレーのポロシャツの小綺麗な男の人が「中国人ですか?」と親しげに話しかけてきた。何者かと思ったら、バグダッドから来た諜報部員だという。私が取材者だと知ると、解説役を買って出てくれた。開口一番、「われわれは国際的な基準に則っている」と話し始めた。
スクリーニングは、複数の海外メディアでかなりの批判を浴びている。この手続きを実施するのは、政権側シーア派の関係者。モスル住民の多数はスンニ派。イラク戦争後の宗派対立で、長年のスンニ派への恨みから、イラク軍あるいは民兵によって〈スクリーニング〉と称する拷問が行われている、と報道されているのだ。諜報部員は、こちらがまだ聞いてもいないのに口を開くとは、メディアを相当気にしているのだろう。
諜報部員がいうスクリーニングの手続きは、基本的には名前の照合だ。政府はイスラム国と関係している人たちのデータベースを持っている。そこに掲載された情報と、IDカードの名前が合致すれば裁判にかけられる。(つまりカラコシュの裁判所で尋問を受けることになる。)ただし、偶然同じ名前の人もいるので、その場合は母親の名前をチェックして、本人か否かを確実にする。あるいは、データベースにない情報もあるので、住民からの情報提供で捕まえることもある。危険な殺人者に限ってはバグダッドまで運ばれるそうだ。諜報員の彼の話を聞いていると、スクリーニングに全く問題はないように思えてくる。
彼は自分の仕事をこう説明した。「私は、犯罪者がバグダッド入りするのを防いでいる。だから、ここは重要な場所なんだ」。彼の関心は、首都バグダッド防衛なのだろう。
機嫌を損ねないように聞いてみる。海外メディアではスクリーニングのさいに拷問が行われている、と報道されていますが、と。諜報部員は動揺することなく話を続けた。「それは軍がやったこと。でもそういうことは起こりうる。なぜならこれは戦争だから」
バグダッドの諜報部員の言い分はこう。「もし76人を殺した犯罪者がいたら、犠牲者のために何ができるのか。そいつに父を殺され、母を殺され、子どもを殺され、みんな殺されたというなら、そいつをどうするべきか。アメリカでも日本でも、世界中、起こりうること。コントロールできないよ。私は、そうするのが正義だと思うし、みんなそう思っている。ここに来る前はそんな(拷問や報復なんて)こと考えもしなかった。でも、もし76人も殺した人間がいたらどうするべきか」
何も言わない私に諜報部員は、彼の苦しみを話した。「6、7日前に子どもに話しかけられたんだ。誰かに姉妹をさらわれたって。『助けて』と泣きつかれたんだ。でも、私が裁判所についていってどう証言すればいい? その子どもが、自分は家族を守れない、と泣くんだよ。そして、僕を守って、と頼まれた。私は、キミを守る、としか言ってあげられなかった」。もちろん彼は、「だからといって自分がこのキャンプにいるあいだは拷問を認めない」と付け足すのを忘れなかった。
小さな子どもに助けを求められても救えないもどかしさに苛まれたとはいえ、目の前でイスラム国に生活を破壊され、家族を殺され、悲しみ、怒り、そして復讐心に駆られた人たちの想い肩代わりするのが当然なのだろうか。政府が復讐を認めてしまったら、何がこの国を支えるのだろう。私的制裁を認めたら、それこそイスラム国と同じになってしまわないだろうか。
対イスラム国作戦でイラクは団結しているようにみえた。また、イラク戦争以前に宗派対立はなかったともいう。しかし、つい最近まで、いや、今でもイラク国内で激しい宗派対立があるのも事実なのだ。対立する感情が消えたわけではない。イスラム国にまつわる問題に触れるだけではイラクはわからない。
仕事が忙しいという諜報部員は、「ニーハオ」と去っていった。
§
イラクはこれからどうなるのだろう。イスラム国に集まるのがモンスターだったらよかったのに、と思う。モンスターであれば退治すればいい。そうではないだけに、街が解放されただけでは、イスラム国のような組織が生まれる芽が摘まれた、と安心はできない。イスラム国はまだ隣にいる。
イスラム国に参加したイラク国民のなかには、富める人も貧しい人も、思想に惹かれた人もお金に惹かれた人も、積極的に協力した人も消極的に協力した人もいる。構成員には特徴すらないのか、と思えるくらい参加の理由は様々だ。それでも感じるのは〈イスラム国〉という名前を聞くと身構えてしまうけれど、人々がイスラム国に参加するのは、もっと何か人間くさいドロドロした感覚、あるいは、誰にでもあるごく当たり前の弱さ、軽薄さにも原因がある気がする。「あんな残酷なことができるなんて人間ではない。信じられない」と憤るのは簡単だ。でも、少し歴史を振り返れば、ルワンダで、ベトナムで、ドイツで、日本で、鉈で殺しあったり、生首を晒したり、玉砕を命じたりしてきた。「イスラム国の罪を許せ」「大したことではない」といいたいのではない。何かの拍子に自分だってそんな行動をとるかもしれない。自分たちとは違う人間だ、と強く線引きをすればするほど、その拍子、はずみに無自覚になりやすいのではないだろうか。あの諜報部員が、率先してひどい拷問をしたりはしないだろうけれど、何かのきっかけで〈反イスラム国〉構成員としてモンスターのようになることだってあり得る。実際、住民のあいだで、イスラム国に協力した人への報復や制裁がすでにはじまっている。正義の基準なんて容易くかわる。
戦闘の後には破壊された街が残った。モスルの損害は数10億ドルに相当するという。瓦礫となった街で途方に暮れた住民たちはどこへ向かうのか。
イスラム国に参加したのはモンスターではなく、となりにいるような人たち。そして、誰にだって気持ちの内側にその種がある。でも、モンスターじゃないからこそ、私たちにも〈理解〉できる。彼らの内に芽生えたものが何だったのか、その芽を育てたものは何か。他人事して分析するのではなく、自らの内に目を向ければ、原因を考えることができるのかもしれない。

Text and Photo by Megumi Ito